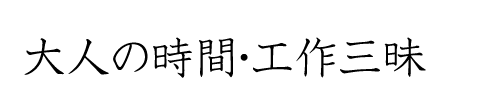上級Raspberry PIをモバイル用に
- モバイル系
概要
Raspberry PIに小さなスクリーンをつけて、モバイルデバイスとして楽しみませんか。
Linux Guiを動かすのもよし、ブラウザーでGoogleカレンダーを表示しておくのもよし、写真を表示するのもかわいいでしょう。さらにDOSを動かすこともできます。
昔、一世を風靡したHP-200LXの利便性をよみがえらせることができるかもしれません。
必要な商品
詳細説明
ハードウェア
Raspberry Pi Bは以外に電気を必要とします。測定すると、1A以上流れています。
パソコンからRaspberry Piを動かすことはあまりお勧めしません。というのも、USB2.0までは規格上の最大電流は0.5Aです。
外付けハードディスクもUSBケーブルが2本ついているものもあります。
モバイルでもって歩く場合、お勧めな電源はスマホ用の充電バッテリーです。スマホも激しく電力を消費しますから、似た用途です。また、数多く売られていますから安く入手できる点も見逃せませんね。
他は専用のケースにディスプレイと小さいWiFiのUSB子機があれば、持って歩けます。
Raspberry PiのOS用にmicroSDカード(8GB以上を推奨)。設定用にUSBドライブがあったほうがよいです。
事前知識
ここでは最初にRaspberry Piで動かすRaspianOS(Linuxの派生)の操作について説明します。
覚えることはふたつです。ひとつはmountコマンド、もうひとつはddコマンドです。
mountコマンドはRaspberry PiにUSBドライブを差し込んで、ディスクとして使用可能にするために使うコマンドです。sudo mount /dev/sda1 /media/xxxという形式です。
ここでxxxはマウントポイントと呼ばれます。sudo mkdir /media/mntなどの名前で作ります。
Raspberry PiではUSBドライブをUSBソケットに差し込むとひとつめならば、/dev/sda1で認識されます。それを上のマウントコマンドでマウントすると、/media以下に内容が見えるはずです。mountコマンド自体についてはLinuxの解説サイトや本を参照ください。
ddコマンドはmicroSDのイメージをmicroSDに書き込むためのものです。
まず、Raspberry Piのディスプレイの動作する機能を含んだイメージファイルをこちらからダウンロードしてください。
Windowsの場合
- Win32Diskimager.exeをこちらからダウンロードします。zipファイルを展開しておきます。
- できあがったWin32DIskImager.exeを右クリックして「管理者権限で実行」をします。
- MicroSDカードをPCに差し込みます。
- 対象SDカードか間違いないことを確認して、書き込みを実行します。
Macの場合
対象SDカードにあるファイルを消すか、ディスクユーティリティで”消去”しておきます。
- ターミナルウィンドウをひらきます
- "df -h"と入力してみます。接続されているディスクを見るコマンドです。
- SDカードをさしこみます
- もういちど、"df -"を入力してみます。SDカードのディスクが発見されるはずです
通常 /dev/disk6s1 などという形式です。 - いったん、それをマウントからはずします。コマンド形式は"sudo diskutil unmount /dev/disk6s1" イメージを書き込みます。コマンド形式は"sudo dd bs=1m if=/Users/****.img of=/dev/disk6"となります。注意点はマウントされている時はdisk6s1などですが、アンマウントしたデバイスの指定は後ろのs1などの記号を外すことです
- 少しかかってコマンドが終了したら勝手にマウントされますから
マウントからはずします。コマンド例"sudo diskutil eject /dev/disk6" - SDカードの完成です
もし、あなたが手作業で最初からaspiOSから設定していくのであれば、次のような手順となります。(こちらのほうがマイコンピューターを理解するという意味ではお勧めです。)
作業シーンを英語ですが、ビデオで見ることができます。(こちらをクリック
- キーボードの設定、ディスプレイの設定
- LAN環境の設定
- RaspberryPiの基本設定でSPIとI2CをONにする。
- FBTFTドライバを入れる。
- /etc/modulesを更新
- /boot/config.txtを更新
- X11の構成ファイルを更新
- /boot/cmdline.txtを更新
先に作ったSDカードから/etc/modules, /boot/config.txt, /boot/cmdline.txtを取り出しておくと参考になると思います。
キーボードの設定、ディスプレイの設定
キーボードは弊社で販売しているものでしたら、トングルをUSBに差し込めば動作します。他にもワイヤレスで使える(安価なロジクールのキーボード)などがオススメです。
ディスプレイはHDMI端子です。ちょっとの間ならテレビで代用してもいいかも知れません。
とにかくネットワークに接続できれば、SSHなどでも操作できます。
LAN環境の設定
ケーブルを差し込む場合は、差し込んでください。DHCPが最初は設定されていますから、お使いの環境がDHCPなら即座につながります。
WIFIの場合、コマンドラインで行うよりも、一度、startxでGUIを立ち上げてください。
MenuでRunをクリックしてください。ここでブランクにwpa_guiと入れて実行してください。
このユーティリティはパソコンのものによく似ているので迷わないと思います。WPA2だとCCMP(暗号化方式のことです)と表示されます。PSKにパスワードを入力してください。
最後にFile->Save Configurationで保管します。
RASPBERRY PIの設定
SPIモジュールを読み込むようにします。
- sudo raspi-configでraspberry Piのコンフィギュレーションを出します。(GUIではありません。Raspberry PIが立ち上がった直後のコマンドラインで行います。Raspberry PIはLinuxなのでコマンドライン操作は必須です。)
- 8 Advanced Optionsを選びます。
- A6 SPIを選択してEnableにします。モジュールを読み込むか?についてもYES
- 同様にA7 I2Cも選択してEnableにし、モジュールも読み込みます。
- 再起動します。(sudo rebootが便利)
次にTFTディスプレイのドライバーをインストールします。
実は多くの小型のディスプレイが生産されていますが、SPI,I2Cで動作させるドライバーはこのNotroというところしか見当たりません。たいていのデバイスがこのドライバーで動作します。
ここのWikiはとても大事です。とくにここを見ると設定する製品番号がドライバーでサポートされているかを調べることができます。
インストールは次のコマンドを間違えないようにコマンドラインからいれてください。
sudo REPO_URI=https://github.com/notro/rpi-firmware rpi-update
いろいろ導入されておわります。
最後にLinuxのカーネルに必要なモジュールのロードとパラメータを渡す作業をします。
/etc/modules, /boot/config.txt, /boot/cmdline.txtの編集ですが、お買い上げになったディスプレイの場合、こちらからダウンロードして、USBメモリーに書き込んでおいてください。
USBメモリーを先に記述したmountコマンドでマウントします。
ファイルをコピーします。
sudo cp /media/mnt/modules /etc/
sudo cp /media/mnt/config.txt /boot/
Raspberry Piのしかるべき場所にコピーします。
これはRaspberry Piに強制的に必要なモジュールを読み込ませる、カーネルに必要なパラメーターを渡すために必要なファイルです。
LCDディスプレイを接続したらブートします。
この時点では画面が黒くなります。
ここでログインしてからcon2fbmap 1 1と入力すると、コンソールになるはずです。
ここからが悩ましいところで、HDMIのディスプレイも使いたいのであれば、毎回、con2fbmap 1 1を入力してください。
そんなことしたくないという方は、次に進みます。
X11の構成ファイルを更新
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.confと入力し、
Optinon "fbdev" "/dev/fb0" を "fbdev" "/dev/fb1"に一文字書き換えます。
これでGUIのコンソールがLCDディスプレイになります。
fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11 logo.nologo
これでまたリブートします。もともとあったHDMIに接続していたコンソールは外してください。
小さいディスプレイですべて可能となり、タッチペンで操作することもできます。
最後に
sudo apt-get update sudo aput-get upgrade
でRaspbianで使われているパッケージを最新のものに更新しておきましょう。よくある質問
現在はありません。
必要な道具
- ・スマホの充電用のパワーパック
- ・パワーパックとRaspBerry PIを接続するUSBケーブル
- ・WIFi子機(USB接続。バッファローのWLI-UC-GNMなど比較的古い機器が確実です)
- ・microSDカード(8GB以上)
- ・microSDカードリーダーUSB接続
- ・USBメモリー
必要な商品を使った他の記事
現在はありません。