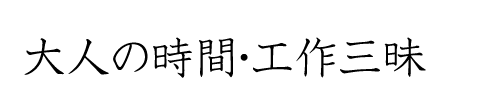初級アルコール検知機
- センサー系
- 気体
概要
アルコールセンサーとGroveのLCDディスプレイを利用してアルコール検知器を作ってみました。
必要な商品
詳細説明
接続
アルコールセンサーは4本の線が出ています。
裏側を見ると、感度調整のボリュームと端子の記号が見えます。
上から5V、DOUT(デジタル出力)、AOUT(アナログ出力)、マイナスです。
ここでデジタル出力とはなにかというと、ボリューム(左下の箱)で調整したしきい値を超えると1(オン)が出力されるものです。
アルコールセンサーの+5V,マイナスはArduinoの電源ピンに、AOut(アナログ出力)はArduinoのアナログ入力のA0に接続してください。
プログラム
アルコールセンサーのアナログ出力ではどれくらいの値が示されるのでしょうか?なにもない状態で25程度、エタノールのボトルから蒸気を吹きかけても500くらいがいっぱいいっぱいでした。
実際に飲んだ人の呼気を調べてもエタノールボトルほどはいかないと思います。
そこでこのプログラムでは、センサーの示す20から450をバーグラフの1から15までの段階で示すことにしました。Arduinoにはとても便利な命令があって、プログラムの42行目にある
map(変換したいデータ, 変換したいデータの最低値, 変換質データの最高値, 変換されるデータの最低値, 変換されるデータの最高値)
と設定すれば割合を勝手に計算してくれる便利な命令があります。
もう少し機能をつけようと、値によってLCDディスプレイのバックカラーの色が変わるようにしてみました。それが50から56行目です。お好み応じて色の変化をつけてみてください。
Groveのアルコールセンサー
Grove製は接続箇所もだいたい決まっているので、簡単です。
テストでは図のようにA0にケーブルを差し込んでください。これでA0(プログラム上では15ピン)でアルコール濃度を検査できます。
よくある質問
現在はありません。
必要な道具
- ・酔っぱらい?
必要な商品を使った他の記事
現在はありません。